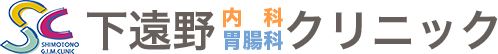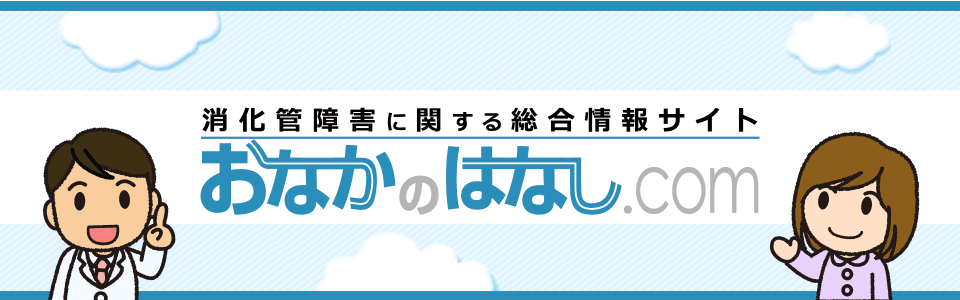ビタミンの種類とそれぞれの働きについて
〇ビタミンの種類
13種類あるビタミンは、脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンの2つに分けられます。
脂溶性ビタミンには、「ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK」の4種類があります。
水溶性ビタミンには、「ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン」の9種類があり、ビタミンC以外はまとめて「ビタミンB群」と呼ばれることがあります。
〇ビタミンの働き
【動物性食品と植物性食品から摂取できるビタミンA】
ビタミンAは、皮膚や粘膜を健やかに保ち、視覚に関わる色素タンパク質の生成、カラダの成長に関わっ ています。豚レバー、鶏レバー、ウナギなどの動物性食品に多く含まれるほか、ビタミンAの前駆体である「プロビタミンA」としてニンジン、ホウレン草などの緑黄色野菜に含まれていることも特徴です。
【カラダの中でも合成されるビタミンD】
ビタミンDは、カルシウムと関わりがあり、カラダづくりをサポートします。適度に日光に当たることで合成されます。ビタミンDを多く含む食品は、鮭、サンマ、ブリ、きのこ類、卵などがあります。
【さまざまな食品に含まれるビタミンE】
ビタミンEは、細胞膜に存在し健康維持を助けます。ビタミンEを多く含む食品は、西洋かぼちゃ、うなぎの蒲焼き、めかじき、アーモンドなどがあります。
【腸内細菌によって合成されるビタミンK】
ビタミンKは、血液凝固や健康維持に関わっています。食事から摂取するほかに、腸内細菌によっても合成されます。ビタミンKを含む食品は、納豆、ホウレン草、小松菜、ブロッコリー、鶏肉などです。
【野菜や果物に多く含まれるビタミンC】
ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持に関わり、植物性食品からの鉄の吸収を促進するほか、カラダの中の酸化還元反応に広く関わっています。加熱調理によって失われやすいことが特徴。野菜や果物に多く含まれており、サラダやカットフルーツなど生のまま食べると調理による損失がなく、効率良く摂取できます。
【エネルギー生産に関わるビタミンB1】
ビタミンB1は糖質代謝などの補酵素として働き、エネルギー生産に深く関わっています。ビタミンB1を含む食品は、豚肉、うなぎ、紅鮭などのほか、玄米や発芽玄米など精製されていない穀類があります。
【特に妊娠中は十分に摂取したい葉酸】
葉酸はDNAやRNAの合成、アミノ酸の代謝などに関わっています。妊娠前からの葉酸摂取が推奨されており、胎児の発育を助けるビタミンです。葉酸を含む食品は、レバー、枝豆、ホウレン草、ブロッコリー、グリーンアスパラガスなどがあります。