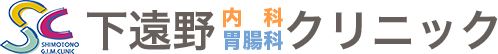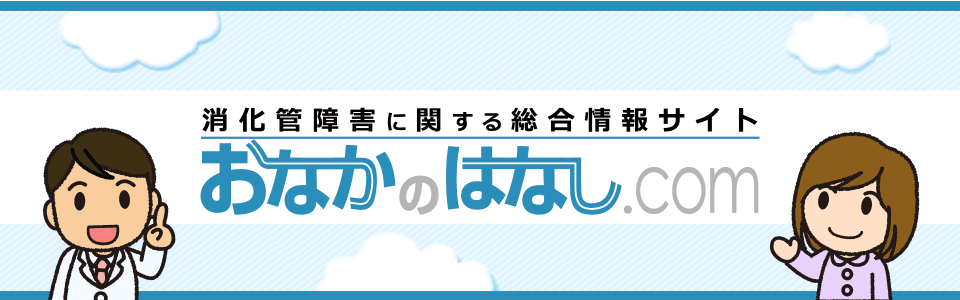腫瘍マーカー検査について
- 検査の目的
腫瘍マーカー検査は、がんの診断の補助や診断後の経過観察、治療の効果判定などを主な目的として行う検査です。腫瘍マーカーとは、主にがん細胞によって作られるタンパク質などの物質で、がんの種類や臓器ごとに特徴があります。しかし、がんかどうかは、腫瘍マーカーの値だけでは診断できません。画像検査や病理検査などその他の検査の結果も併せて、医師が総合的に判断します。
- 検査の方法
腫瘍マーカー検査は、血液や尿などに含まれる腫瘍マーカーの量を測定して行います。
腫瘍マーカーの値は、一般的に体の中にあるがんの量が増えると高くなり、減少すると低くなると考えられます。このことを利用して、体内のがんの量を推定し、がんの経過や治療の効果などについて調べます。がんの種類によっては複数のマーカーを組み合わせて検査することもあります。
- 検査の特徴
腫瘍マーカーの値は、体の中にあるがんの量を反映する指標として用いられますが、がん以外の疾患の影響で、がんがなくても高くなることがあります。加齢や妊娠、月経、飲酒、喫煙、薬の成分などが、がんの量とは無関係にマーカー値に影響することもあります。
このように、腫瘍マーカーの値だけでは診断ができないため、診断の参考になる検査の一つとして、画像検査やその他の検査とともに行います。また、全てのがんについて腫瘍マーカーが見つかっているわけではございません。
4.腫瘍マーカー検査を行う主ながん
・甲状腺がん:CEA
・肺がん:シフラ、CEA、ProGRP、NSE
・食道がん:SCC、CEA
・胃がん:CEA、CA19-9
・大腸がん:CEA、CA19-9
・肝臓がん(肝細胞がん):AFP、PIVKA-Ⅱ、AFP-L3分画
・胆道がん:CA19-9、CEA
・すい臓がん:CA19-9、Span-1、DUPAN-2、CEA、CA50
・腎盂、尿管がん:NMP22
・膀胱がん:NMP22、BTA
・前立腺がん:PSA
・乳がん:CEA、CA15-3
・子宮頸がん:SCC、CA125、CEA
・卵巣がん:CA125
☆当院のワクチン接種実施期間のお知らせ☆
インフルエンザ:1歳から64歳まで:令和7年10月1日~令和7年12月27日まで(高齢者:令和7年10月16~令和7年12月27日まで)となります。
新型コロナウイルス:令和7年10月15日~令和8年 3月31日まで